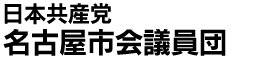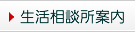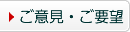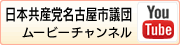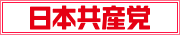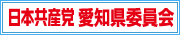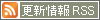青木ともこ議員の個人質問②アクティブ・ライブラリー構想の見直しを(2017年9月14日)
なごやアクティブ・ライブラリー構想(案)の見直し
青木ともこ 議員
15万冊の図書館ができる一方、1万冊まで減らされる図書館ができる。図書館格差が生まれるのではないか
【青木議員】教育委員会は、今年6月28日、図書館サービス網の再構築と運営体制の見直しをめざす「なごやアクティブ・ライブラリー構想案」を公表し、策定を進めています。
名古屋市図書館すべてに関わるこの構想案は、市民ニーズの変化と厳しい財政状況に対応し、効果的で効率的な図書館運営で、サービスの向上を図る、としていますが、名古屋のまちの図書館がどう変わるのでしょうか。
現在、市内には21の市立図書館があります。構想は、市域を5つのブロックに分け、ブロック内の図書館を、A、B、C、その他とタイプ分けし、Aタイプは直営で蔵書15万冊とする他は、Bタイプ5万~7万冊、Cタイプは1万冊で、その他に貸出し返却ポイントなど、ともに運営は民間活力でとしています。
これまでの図書館は、1区1館方式で整備され、各館の蔵書は平均9万冊を超え、支所館でも約7万冊を備えており、市内どこに住んでいても、等しく図書館サービスが受けられるようにと運営されてきました。
しかし、今回の構想案に当てはめると、ブロック内の各館で蔵書に差が生じ、たとえば 、こちらの館で読みたい本が無ければ、よその館に行くか取り寄せる、という具合に、不便な図書館になりはしませんか。しかも、蔵書1万冊のCタイプに至っては、お話し会行事もなし、としています。お話し会は、どこでも若い親子に人気があり、わらべ唄の会など、小さなお子さ
、こちらの館で読みたい本が無ければ、よその館に行くか取り寄せる、という具合に、不便な図書館になりはしませんか。しかも、蔵書1万冊のCタイプに至っては、お話し会行事もなし、としています。お話し会は、どこでも若い親子に人気があり、わらべ唄の会など、小さなお子さ ん連れで賑わっています。教育委員会は、図書館のタイプ分けについては、今後検討するとしていますが、身近な図書館からお話し会が無くなれば、子どもを抱えて遠くの図書館まで行かなければならない、それもありえると承知の上でしょうか。
ん連れで賑わっています。教育委員会は、図書館のタイプ分けについては、今後検討するとしていますが、身近な図書館からお話し会が無くなれば、子どもを抱えて遠くの図書館まで行かなければならない、それもありえると承知の上でしょうか。
市民の身近な図書館にお話し会のあるところとない所が出来る、15万冊もの豊富な蔵書の図書館がある一方、わずか1万冊にまで減らされてしまう図書館もある、これは、図書館に格差が生まれるということではありませんか。
市民ニーズの変化を踏まえた新たなサービス網を構築(教育長)
【教育長】図書館は、地域における情報の拠点であり、公共図書館の役割として、すべての市民にサービスを提供していく責務がある。
図書館の利用は、月1回以上の利用者が約2割、年間1点以上の本などを借りた市民は約1割にとどまり、交通の便がよい図書館の入館者数が多い状況で、図書館を利用する主な目的の約7割が本などの貸出返却となっている。
こうした状況や市民ニーズをふまえ、駅などの便利な場所での貸出返却口や、福祉施設への出張サービスなど、新たなサービスをネットワークとして展開することで、誰もが気軽に利用しやすいサービス綱の再構築を検討していきたい。
保有資産の10%削減という一律的な総量規制を、図書館にあてはめることについて、教育的視点から妥当とする理由はなにか
【青木議員】これまでの図書館のあり方を大幅に改編するこの構想の具体案を、教育委員会は、6月末に突然公表し、パブリックコメントを経て、10月には策定をするとしました。わが党は、市民や図書館利用者に十分知らせないまま、いきなり意見公募に付すのは拙速過ぎると指摘し、パブリックコメントを見合わせ、すべての図書館で構想案の説明会を開くよう申し入れました。
これを受けて、当初予定されなかった説明会が8月19日に開かれました。当日は定員50名を大幅に超える参加で会場は一杯となり、参加者からは、「構想がわかりにくい」「市民への周知が不十分」などの意見が相次ぎました。また。民営化の拡大で、これまでどおり図書館の役割が果たせるのか、この点に質問が集中しました。
担当者は、「図書館本来の役割は承知している」と説明しつつ、一方できびしい財政と保有資産削減の方針がある、と強調しました。これには、「財政難ばかり強調している」「教育委員会の提案とは思えない」との指摘が相次ぎ、質問の手が次つぎあがるなか、説明会は打ち切られました。
今回の構想案にも、「市設建築物再編整備の方針」が強く反映されています。2050年までの保有資産10%削減を前提に、図書館の複合化や売却まで視野にあるとのことですが、「削減目標」が独り歩きしてはいませんか。そこでうかがいます。
保有資産の10%削減という一律的な総量規制を、図書館という、その地域に根付いた社会教育施設にあてはめることを、教育的視点から妥当とする理由はなんですか。お答えください。
図書館の整備についても、「市設建築物再編整備の方針」をふまえる(教育長)
【教育長】「再編整備の方針」では単なる削減ではなく、様々な工夫で多くの市民がサービスの充実感を得られるよう、縮充の精神で取り組むこととされ、図書館の整備も、この方針をふまえ、 全体の保有資産量の適正化を図りつつ、施設の効率的な再編を行うが、運営面などを工夫することで、市民サービスを維持・向上したい。
民間活力の導入で、図書館事業の継続性と安定性、水準の維持と向上などが図れるのか。直営ではできない理由はなにか
【青木議員】教育委員会は、構想案のなかで、近年、図書館利用層が広がらない一方、カフェの設置やネット環境の充実など、新しいニーズが増え、対応が必要としていますが、本市の図書館利用は年間のべ約325万人に約1173万点を貸し出し、行事参加などの来館を合わせると約654万人にのぼり、この10年間、ほぼ横ばいで推移しています。
この数字をもって、構想案が示すような、大幅な図書館再編が必要なのか、大いに疑問です。むしろ、これまで1区1館方式で、どこに住んでいても、等しくサービスが受けられ、図書館司書の努力もあって、全体として高い市民利用を維持してきたのではないでしょうか。新しいニーズへの対応も一つの課題ですが、改めるならば、まず図書予算を見るべきです。
本市の図書購入費は、ここ20年で半分にまで減らされました。毎年市民から、「新しい本を買って欲しい」「頼んだ本が届かない」と苦情が出るのも当然です。
日本図書館協会の調査では、2017年度の図書館資料費を20政令市で比較すると、本市は人口1人あたり78円。下から数えて5番目です。構想案は、図書館ニーズについて色々説明していますが、本市では図書費が年々削られ、他の政令市に比べても低い。こういった事情には触れていません。
構想案では、市内全体で6館だけを直営とする他は、すべて民間活力とし、図書館司書も、直営6館に集約化する方針です。民間活力には、様々ありますが、指定管理者制度については、近年、多くの問題が指摘されています。総務省2015年の調査では、指定管理者制度の導入率は、全国で約15%程度で500館程度、うち12図書館は、導入後、直営にもどしたことも判っています。図書館法が定めるように、自治体の責任で運営する図書館には、事業の継続性と安定性が求められますが、短い指定期間では図書館本来の機能確保が難しい、この制度は図書館にはなじまないということを、国も認めています。このような事情を、教育委員会は承知していると思いますが、ここでおたずねします。
民間活力の導入拡大で、図書館運営に求められる事業の継続性と案定性、水準の維持と向上などが、図れるとお考えですか。また、直営ではそれが出来ない理由はなんでしょうか。
現在は窓口等業務委託を実施し、指定管理者制度を試行実施中(教育長)
【教育長】図書館では現在、分館で窓口等業務委託を実施し、指定管理者制度を試行実施している。
「構想案」は、鶴舞中央図書館のほか5図書館を直営にし司書を集約して専門的サ一ビスの向上を図る。直営と民間活力を組み合わせて効率化を図りながら、直営館が民間活力を導入する図書館を支援して事業の継続性や安定性を確保し、全体として図書館サービスを向上させていきたい。
市民に十分知らされていない。構想の見直しを(意見)
【青木議員】教育 長の答弁ですが、こちらの質問に明確に答えておられません。蔵書の差やお話会行事のあるなし、格差についておききしたのに、答えは図書館利用の状況の説明でした。これでは、市民の利用はこの程度だから、蔵書を減らし、お話会をなくしても仕方がない、このように聞こえます。
長の答弁ですが、こちらの質問に明確に答えておられません。蔵書の差やお話会行事のあるなし、格差についておききしたのに、答えは図書館利用の状況の説明でした。これでは、市民の利用はこの程度だから、蔵書を減らし、お話会をなくしても仕方がない、このように聞こえます。
また、保有資産10%削減については、教育的視点がほとんど読み取れないお答えでした。民間活力については、希望的観測ばかりで、指定管理者制度など課題をどう捉えているか、図書館本来の役割をどう維持するのか、はっきりした根拠は示されませんでした。
アクティブ・ライブラリー構想案は、8月にパブリックコメントを終え、いま集約中とのことですが、相当数の意見が届いているとお聞きしました。内容については、市民が構想案をどう受け止めているか、しっかりと精査していただくことを強く要望いたします。この構想案は、市民に十分知らされないまま、パブリックコメントにふされました。先の説明会の状況を見ても、市民に理解されたとは言えない状況です。構想案の課題も払しょくされていないことから、なごやアクティブ・ライブラリー構想案の見直しを強く求めます。