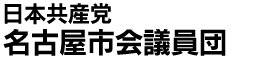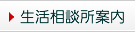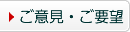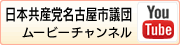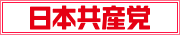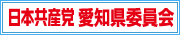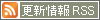2025年2月定例会
2025年2月定例会 本会議 田口一登議員の議案質疑
児童虐待防止条例改正案について 児童相談所の人材育成・体制強化を
今回の条例改正に込めた提案者の思いは
【田口 一登議員】
児童を虐待から守る条例の一部改正案について質問します。
本条例が2013年に制定されてから10年余、本市の児童虐待防止対策は、3か所目となる東部児童相談所の新設、緊急介入班への弁護士の配置と緊急介入・初期対応班への再編、虐待を受けた子どもの家庭復帰支援事業の本格実施など、体制や事業において前進しています。一方で、児童虐待相談の対応件数は、この間に2倍以上に増加しており、さらなる施策の充実が求められています。
そこでお尋ねします。議員提案で制定された本条例が、虐待から子どもを守る施策を推進する上で、どのような役割を果たしてきたと認識されているのか。また、さらなる施策の充実のために何が課題となっているのか。今回の条例改正に込めた提案者の思いを伺います。
【塚本 つよし議員】
ただいま提案内容について、大きく四つの視点からお尋ねをいただきました。
まず本条例が虐待から子どもを守る施策を推進する上でどのような施策の充実のために何が課題かについてです。名古屋市児童虐待から守る条例は、児童の命を守る安全を確保することを主眼に制定したものでございます。本条例には警察をはじめとした関係機関との情報共有を進めることや一時保護を積極的に運用していくこと、本市独自の5月と11月の年2回の虐待防止推進月間を定めるなど児童虐待の早期発見、早期対応に必要な取り組みを規定し、これらは本市の児童虐待対策の指針となり、また児童相談所における虐待相談対応においても定着してきたものと認識をしております。一方、提案説明の中でも申し上げましたように、本市の児童虐待対応件数が高止まりの状況にあります。これまで行っている虐待への対応を「川下」に例えるならば 虐待そのものをなくしていくため、「川上」となる虐待の発生予防や、さらには虐待を受けた子どものケアに力を入れていく必要があるところです。
条例施行から10年以上が経過し、本条例の制定を提案した3会派の責任として、本市の児童虐待対策の将来を見据え、引き続き本市の指針となるよう、このたびの改正案を提示、提案するものでございます。
人材の育成や体制の強化
【田口 一登議員】
私は、児童相談所における人材の育成や体制の強化は、引き続き重要な課題だと考えています。
改正案の第9条「人材の育成」では、「虐待の防止に関する専門的な知識及び技術を有する職員を育成するため、児童相談所等の人材育成に係る体制の整備及び強化を図る」との項が追加されています。
児童相談所で虐待を受けた児童の保護や相談に対応し、専門的な技術に基づいて必要な指導を行っているのは児童福祉司や児童心理司です。この間、増員が図られ、児童福祉司と児童心理司の人数は来年度、国の基準を満たすと聞いていますが、一方で、現場の職員から、「新規の職員や相談業務は初めてという職員が、虐待した親への介入や複雑な背景を持つ子どもへの対応などで苦悩し、メンタルを病んだり、早期に異動したりしている」という話を聞いています。
育成するとされている「専門的な知識及び技術を有する職員」とはどういう職員か、また、どのような人材育成体制の整備が望まれているのか、お尋ねします。
【塚本 つよし議員】
続きまして、9条の「専門的な知識および技術を有する職員」とはどういう職員か、どのような人材育成体制の整備が望まれているかについてです。児童虐待の対応に従事する児童相談所等の職員については、虐待に関する知識は当然のこと、社会福祉制度等の福祉的な知識や、民法などの法的な知識など様々な専門的知識が必要になるとともに、保護者を説得したり、子どもとの信頼関係を作ったりするために、面接スキルといった技術も必要になります。
こうした知識や技術は容易に身につくものではなく、一定の時間や手間をかけて人材を育成していく必要があります。改正案については、例えば研修企画運営の専任体制の構築や児童福祉司等が集中的にトレーニングを受けられるような研修環境などを整備することを想定しているものでございます。
一時保護所においては人員不足
【田口 一登議員】
一時保護所においては人員不足が課題となっており、2022年度に実施された中央児童相談所の一時保護所を対象とした第三者評価では、「人員確保の難しさから少ない人員で対応せざるを得ないことから時間外労働が勤務帯によって常態化している」と指摘されています。
改正案の第24条「虐待の防止等に係る体制の整備」では、体制の整備に関して「社会情勢の変化に対応した」という文言が挿入されていますが、これは職員の増員など体制の強化をさらに促進するという意図を込めたものと理解してよいか、お答えください。
【塚本 つよし議員】
次に、24条の社会情勢の変化に対応した体制整備は、職員増員などの体制強化を促進するという意味とかについてです。児童相談所では子どもの安全確保を最優先の取り組みを進める中で、虐待に対して毅然とした態度をとりつつ、同時に家族再統合を図っていくことが求められるようになってきたとともに、令和7年6月から一時保護に係る地方審査制度が開始され、支援の進行管理など、組織的対応が重要になってきております。
今後も制度改正などが想定される中で単に職員増をしていくのではなく、効率的な組織運営を行いながらも、社会情勢の変化を踏まえた上で、必要な組織体制強化を図っていくという趣旨から追加したものでございます。
一時保護施設の環境の整備や運営の改善
【田口 一登議員】
改正案では第19条として「一時保護施設の環境整備」が追加されています。2022年度実施の一時保護所に対する第三者評価では、児童福祉司等との「スピーディかつ確実な情報共有の仕組みの構築」などが改善点として指摘されています。ハード面では、定員が満床になることが常態化していることによる居室の確保、集団生活に慣れない子どもへの個室の提供なども課題としてあげられています。
一時保護所は、虐待など危機的な状況に遭遇した子どもたちが、家族や親しい友だちから引き離されて、情緒的に不安定な中で、集団で生活する場であることから、一人ひとりの発達段階や状況に応じた適切な支援が求められます。
条例に一時保護施設の条文を追加することは、一時保護施設の環境の整備や運営の改善を促進することにつながると考えますが、この条文を追加したねらいについてお伺いして、質問を終わります。
【塚本 つよし議員】
最後に19条の一時保護施設の環境整備の条文を追加した狙いについてでございます。一時保護される子どもの中には、虐待の影響などにより、他害行為に及んだり、精神的に不安定だったりするなど、様々な状況の子どもがいますが現状では管轄の児童相談所の一時保護所で、集団生活を送る形になっております。本来、一時保護所は虐待を受けた子どもにとって安心安全を感じられる場所でなければなりませんが、こうした環境において、落ち着いて過ごすことが難しく、ストレスを感じている子どもがいると聞いております。一時保護所が虐待以外からの回復に向けた適切なケアが行われる環境等となるよう、議員ご指摘の方法含めてとりくむべき指針として規定を設けたところでございます。以上で終わります。
キーワード:田口かずと